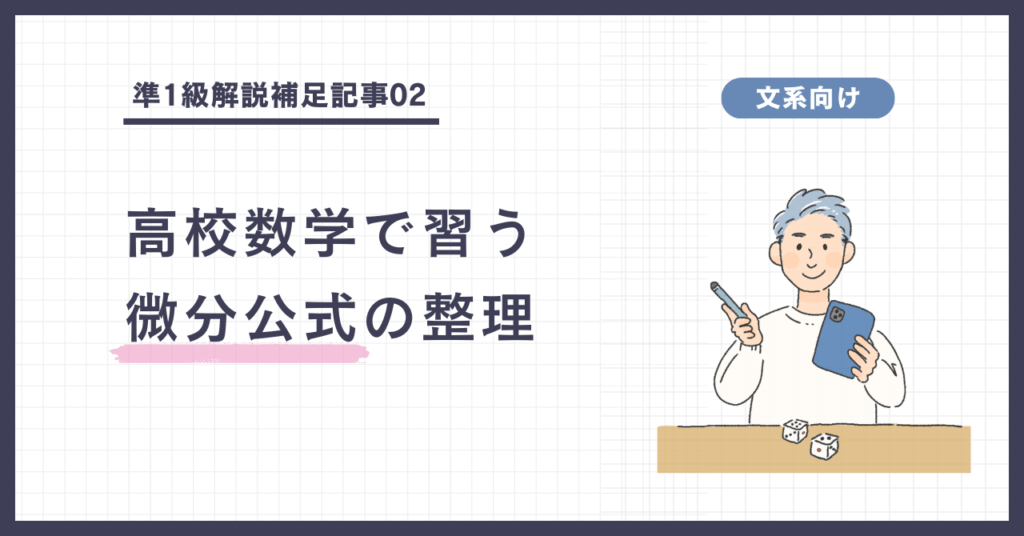
今回は、高校数学で登場する微分の基本公式を、できるだけやさしく整理して紹介します。どの公式も「 \(y = f(x)\) を \(x\) について微分するとどうなるか」という形で見ていきます。※各公式の証明を行うものではなく、ひととおりの公式の整理を目的とした記事になります。
01. 微分とは
「微分」とは、変化の速さを求める操作です。例えば、位置 \(y\) が時間 \(x\) によって変化するとき、その変化のしかた(速さ)を調べるのが微分です。
グラフでいえば、関数 \(y=f(x)\) の曲線に引いた接線の傾きを求めることと同じです。関数 \(y=f(x)\) のある点における傾きを「微分係数」と呼び、この値を変数 \(x\) に対して一般化したものが「導関数」 \(f'(x)\) です。
02. 微分記号
関数 \(y = f(x)\) を微分した結果は、次のように表します。
\[\frac{dy}{dx} = f'(x)\]
どちらも同じ意味で、「 \(y\) を \(x\) で微分した」ということを表します。
03. 基本の微分公式
ここからは、高校数学でよく登場する微分公式を順に確認していきましょう。すべて、関数 \(y = f(x)\) の形で示します。
(1) べき乗の微分
関数 \(y = x^n\) を \(x\) について微分すると、
\[\frac{dy}{dx} = n x^{n-1}\]
となります。右肩の指数が前におりてくるのと同時に、右肩の指数が「マイナス1」されています。
例えば、 \(y = x^3\) のときは \(\dfrac{dy}{dx} = 3x^2\) 、 \(y = x^{-2}\) のときは \(\dfrac{dy}{dx} = -2x^{-3}\) になります。
(2) 定数や定数倍の微分
定数(数字だけの値)は微分すると \(0\) になります。
\[y = a \quad \text{ならば} \quad \frac{dy}{dx} = 0\]
また、関数に定数が掛かっているときは、その定数を前に出したまま微分します。
\[y = a f(x) \quad \text{ならば} \quad \frac{dy}{dx} = a f'(x)\]
例えば、 \(y = 5x^2\) のときは、 \(\dfrac{dy}{dx} = 10x\) になります。
(3) よく使う関数の微分公式
ここで、特によく使う関数の微分結果を一覧にしておきましょう。これを覚えておくと、この後に紹介する例が理解しやすくなります。
| 関数 \(y=f(x)\) | 導関数 \(dy/dx=f'(x)\) |
|---|---|
| \(\sin x\) | \(\cos x\) |
| \(\cos x\) | \(-\sin x\) |
| \(\tan x\) | \(1/\cos^{2}x\) |
| \(e^{x}\) | \(e^{x}\) |
| \(\ln x\) | \(1/x\) |
これらは高校数学のいろいろな分野で登場します。特に \(e^x\) と \(\ln x\) は、統計学でも頻繁に使われます。
なお、 \(e\) は「自然対数の底」で「ネイピア数」と呼ばれるもので、具体的にはおよそ \(2.718\cdots\) という値になります。この \(e\) については、\(e^x\) を微分すると \(e^x\) のままとなるという特徴があります。
また、 \(\ln\) は「自然対数」を意味します。自然対数は、底が \(e\) の対数のことを指し、 \(\log_{\,e}x=\ln x\) です。 \(\ln x\) を微分すると \(\dfrac{1}{x}\) になるという特徴があります。
(4) 足し算と引き算の微分
2つの関数の和および差として得られる関数の微分は、それぞれの関数を別々に微分して、あとで足したり引いたりすれば大丈夫です。
いま、2つの関数 \(f(x)\) と \(g(x)\) を用いて、 \(y=f(x)+g(x)\) と表せる(つまり、関数の和として表せる)ならば、
\[
\dfrac{dy}{dx}=f'(x)+g'(x)
\]
となります。また、2つの関数 \(f(x)\) と \(g(x)\) を用いて、 \(y=f(x)-g(x)\) と表せる(つまり、関数の差として表せる)ならば、
\[
\dfrac{dy}{dx}=f'(x)-g'(x)
\]
となります。
例えば、 \(y=x^{2}+\sin x\) を \(x\) について微分することを考えてみましょう。「足し算の微分」、「べき乗の微分」、「三角関数の微分(上記の「(3) よく使う関数の微分公式」でご紹介したもの)」を用いて、以下のように導けます。
\[\begin{align*}
\dfrac{dy}{dx}&=f'(x)+g'(x)\\
&=(x^{2})’+(\sin x)’\\[5pt]
&=2x+\cos x
\end{align*}\]
(5) かけ算の微分(積の微分公式)
2つの関数の積として得られる関数の微分は、片方の関数ごとに微分して足し合わせるようにして微分を行います。
いま、2つの関数 \(f(x)\) と \(g(x)\) を用いて、 \(y=f(x)g(x)\) と表せる(つまり、関数の積として表せる)ならば、
\[
\dfrac{dy}{dx}=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)
\]
となります。例えば、 \(y=x^{2}\sin x\) のときは、
\[\begin{align*}
\dfrac{dy}{dx}&=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)\\[5pt]
&=(x^{2})’ \sin x+x^{2} (\sin x)’\\[5pt]
&=2x \sin x + x^{2} \cos x
\end{align*}\]
となります。
(6) わり算の微分(商の微分公式)
関数の商(わり算)として得られる関数、つまり、分数の形をした関数を微分するときは、商の微分公式を使います。
いま、2つの関数 \(f(x)\) と \(g(x)\) を用いて、 \(y=\dfrac{f(x)}{g(x)}\) と表せる(つまり、関数の商として表せる)ならば、 商の微分公式は以下のように表されます。
\[
\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\bigl( g(x) \bigr)^{2}}
\]
例えば、 \(y\) が以下のような関数の商として表される場合を考えてみます。
\[
y=\dfrac{x-1}{x}
\]
この式の \(x\) についての微分は、商の微分公式を用いて以下のように導けます。なお、分子を \(f(x)=x-1\) とし、分母を \(g(x)=x\) としています。
\[\begin{align*}
\dfrac{dy}{dx}&=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\bigl( g(x) \bigr)^{2}}\\[6pt]
&=\dfrac{(x-1)’x-(x-1)(x)’}{\bigl( x \bigr)^{2}}\\[6pt]
&=\dfrac{1\times x-(x-1)\times 1}{x^2}\\[6pt]
&=\dfrac{1}{x^2}
\end{align*}\]
(7) 逆数の微分
関数の逆数とは、「1をその関数で割った形」のことです。つまり、以下のような形をしています。
\[
y=\dfrac{1}{g(x)}
\]
このような関数の微分について、以下のような微分公式が成り立ちます。
\[
\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{g'(x)}{\bigl( g(x) \bigr)^{2}}
\]
実はこの公式は、商の微分公式において、分子の関数が \(f(x)=1\) となる場合として導かれます。商の微分公式を \(f(x)=1\) として整理すると以下のように逆数の微分公式が導かれます。
\[\begin{align*}
\dfrac{dy}{dx}&=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\bigl( g(x) \bigr)^{2}}\\[6pt]
&=\dfrac{(1)’g(x)-1\times g'(x)}{\bigl( g(x) \bigr)^{2}}\\[6pt]
&=\dfrac{-g'(x)}{\bigl( g(x) \bigr)^{2}}
=-\dfrac{g'(x)}{\bigl( g(x) \bigr)^{2}}
\end{align*}\]
(8) 合成関数の微分(チェーンルール)
関数の中にさらに関数が入っている(いわゆる「入れ子構造」の)関数のことを合成関数と呼びます。合成関数の微分においては、チェーンルール(連鎖律)を使います。
いま、2つの関数 \(f(x)\) と \(g(x)\) があるとします。ここで、 \(g(x)\) の結果をさらに \(f\) に代入した関数
\[
y=f \bigl( g(x) \bigr)
\]
を考えます。このとき、 \(y\) の \(x\) についての微分(導関数)は以下の公式で導かれます。
\[
\dfrac{dy}{dx}=f’ \bigl( g(x) \bigr) \cdot g'(x)
\]
つまり、外側の関数を微分して、続いて、内側の関数を微分する、というルールです。これを「連鎖的に微分する」という意味で「チェーンルール」とも呼びます。
例えば、いま \(y=\ln(x^{2}+1)\) という関数を考えます。この関数は、外側が \(f(u)=\ln(u)\) で、内側が \(g(x)=x^{2}+1\) の合成関数といえます。したがって、チェーンルールにしたがって、以下のように導関数を導けます。
①外側の関数を微分する
\[
f'(u)=\bigl( ln(u) \bigr)’=\dfrac{1}{u}
\]
②内側の関数を微分する
\[
g'(x)=\bigl( x^{2}+1 \bigr)’=2x
\]
③チェーンルールに当てはめる
\[\begin{align*}
\dfrac{dy}{dx}&=f’ \bigl( g(x) \bigr) \cdot g'(x) \\[6pt]
&=\dfrac{1}{g(x)} \cdot g'(x)\\[6pt]
&=\dfrac{1}{x^{2}+1} \cdot 2x = \dfrac{2x}{x^2+1}
\end{align*}\]
04. まとめ
以上が基本的な微分公式になります。これらの(1)から(8)の微分公式をおさえておくだけで、テキストを読み進める際に混乱する回数がある程度減らせるはずです。
確かにこれらの公式をただ暗記するだけでは不十分で、それぞれの公式の数学的な証明も確認しておきたいところです。 しかし、学習を進めるなかで「とりいそぎ最低限の公式だけ把握しておけば学習がスムーズに進むのに…」というケースがあるのも事実だと思います。
本記事はそういったケースでお役に立てるのではないかと考えております。少しでも学習のお役に立てますと幸いです。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
以下のコース①で微分積分の公式に関してさらに詳しく動画で解説しています。また、コース②は準1級対策の最初の一歩としておすすめです。

